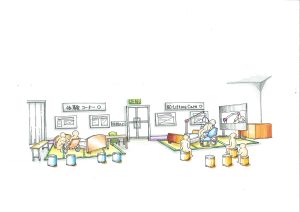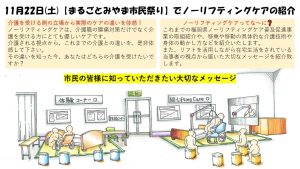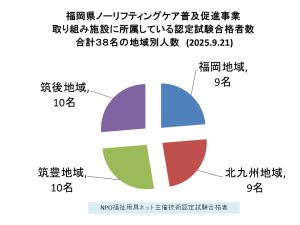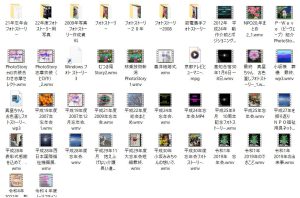毎日、本当に慌ただしい日々が続いていますが、その合間に、ようやく情報誌の編集ができたので、昨日は印刷依頼へ。
といっても、いつも最終の校正はよしみ工産様に助けていただいています。
よしみ工産様には本当に感謝しています。
手渡しで印刷依頼をする時間もなく、入り口に必要な原稿類を吊り下げての依頼。
そして、開発支援のために企業に訪問に出かけていました。
でも、外出先から帰宅したら、今度は友人が新米をたくさん持ってきて下さいました。
実は、毎年、その友人からお米をいただいているのでお米を買ったことがなく、お米の価格高騰やお米不足の今の時期、改めて感謝しなければと思いました。
本当に、食生活まで助けていただいているのですよね。
嫌な事もあるけれど、優しさに触れるたくさんの喜びもあります。
身体は忙しすぎてきついこともありますが、幸せだと思います。
気遣って電話もして下さる方もいます。
お友達の皆さん、いつもありがとうございます。